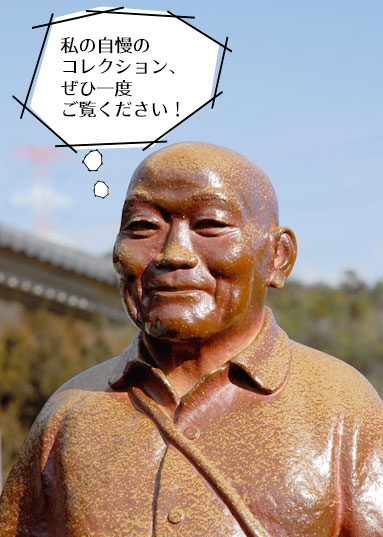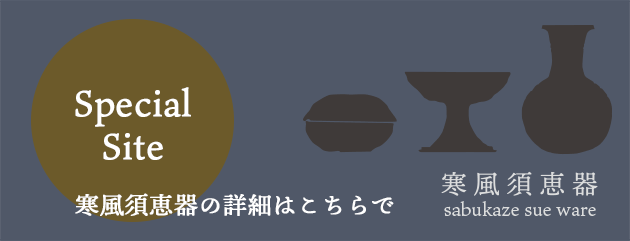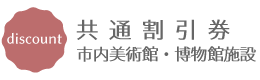News & Topics
- 23.09.27
- 寒風陶芸会館展示の市所蔵須恵器資料3Dモデル閲覧サイト
- 23.02.01
- FAX番号が変わりました
- 22.10.01
- 館長あいさつ 新館長が就任しました
- 22.09.11
- 利用料金改定のお知らせ
会館営業カレンダー
月曜及び祝祭日の翌日が休館日です。月曜が祝祭日の場合と祝祭日の翌日が土・日曜の場合は開館いたします。
※臨時休館日もございます。ご来館の際には、事前にご確認くださいませ。
(ピンク色の日付)=休館日です
国指定史跡
寒風古窯跡群
岡山県南部、瀬戸内市と備前市には、古墳時代後半から平安時代末(およそ1450年前から1000年前)までの約450年間に、130基あまりの「須恵器」と呼ばれる陶器を焼いた窯があったことがこれまでの調査により分かっています。これらの窯跡は総称して「邑久古窯跡群(おくこようせきぐん)」と呼ばれており、さらにこの「邑久古窯跡群」の最南端に位置しているのが「寒風古窯跡群(さぶかぜこようせきぐん)」です。当時焼かれていた「須恵器」は、現在もこの地域で生産が盛んな備前焼の始まりになったとされています。
寒風陶芸会館では、この古窯跡群より出土した資料を保管、展示するとともに、専任スタッフによる来館者へのガイダンスも承っております。
※20名様以上の団体で見学をご希望のお客様は、お電話もしくは予約フォームから事前にご予約をお願いいたします。
寒風陶芸教室
寒風陶芸会館では、「手づくり」「土ひねり」の楽しさを体験していただける陶芸教室を常時開催しております。日常使いの陶器から本格的な備前焼まで様々な作陶体験をご用意しております。1名様より100名前後の団体様まで受け入れ可能です。
窯詰めから火入れ、窯出しまでご自由にご利用いただける登り窯の貸利用も承っております。
寒風作家協議会
寒風陶芸会館のある瀬戸内市には、多くの陶芸作家が陶房を構え、日々、土と向かいながら暮らしております。会館では作家の皆さんとともに協議会を立ち上げ、陶芸への関心を高め、奥深い陶芸の世界を広く紹介することを目的に季節ごとの展覧会や陶芸イベントなどを企画しております。作品の展示と販売も会館にて常時行っておりますので、手仕事の温かみが伝わる素晴らしい作品の数々を手に取ってご覧いただくことができます。
寒風ボランティア協議会
市民グループ「寒風ボランティア協議会」は寒風古窯跡群の発掘に尽力を注いだ「もくすいさん」こと時実黙水氏の意思を引き継ぎ、史跡の保全や研究、史実の実証実験などを行っていこうと設立されました。通常は、一般向けの説明会や講師を招いた勉強会を開催していますが、古窯跡で多数発掘されている鴟尾(しび)という屋根飾りの複製や須恵器窯の復元に取り組むなど実践的な活動も意欲的に行っております。興味をお持ちでしたらどなたでもご入会いただけますので、お気軽にお問い合せ、お申し込みください。